豆知識
【雨どい修理も即日対応】雨漏り対策はプロにおまかせ
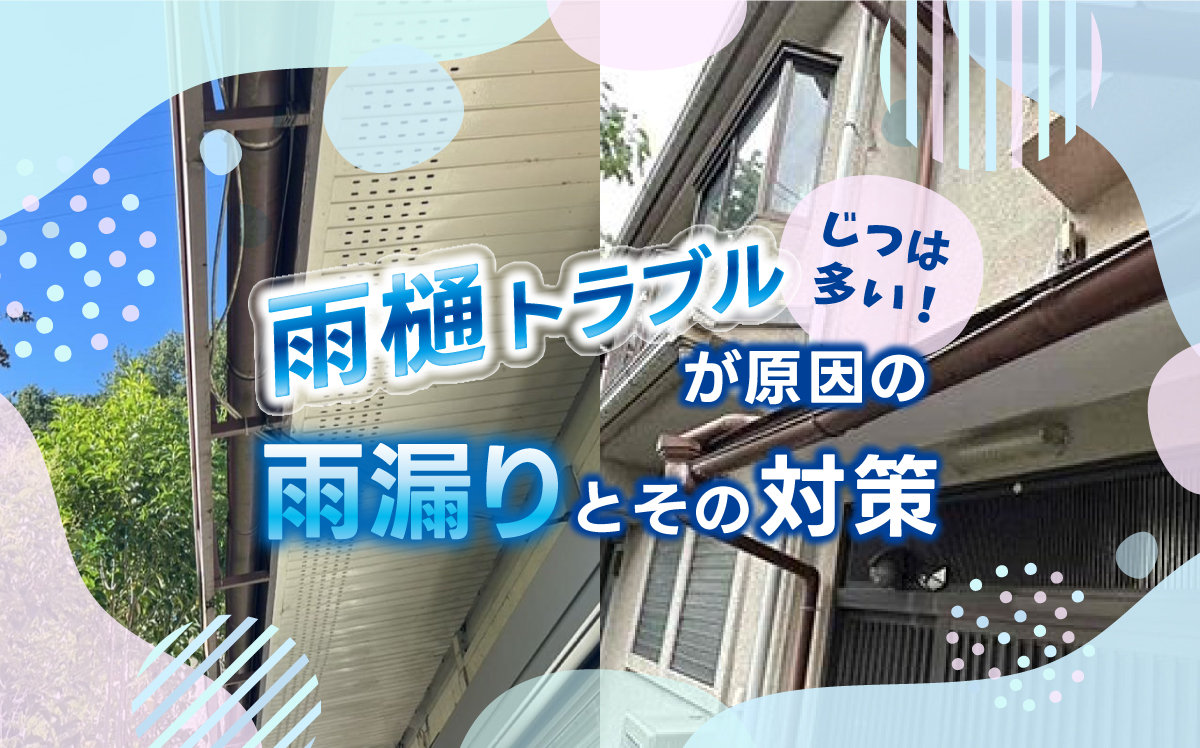
「雨漏りが起きたら、まず屋根を確認」と思われがちですが、実は雨樋の不具合が原因で雨漏りが発生するケースも非常に多いです。
雨樋は屋根に降った雨水を地面へ導く役割を持っています。しかし、詰まりや破損、ゆがみがあると水が正しく流れず、外壁や基礎、さらには家の内部にまで被害が広がることがあります。
特に秋は台風や秋雨前線による大雨が増える時期。雨樋のトラブルを放置すると、雨漏りの被害が一気に悪化する危険があります。
今回は、そんな雨樋トラブルを防ぐために、当社で実際に行った施工事例も交えながら、具体的な対策をご紹介します。ぜひご参考にしてみてください!
施工事例 その1

【ご依頼内容】
「雨が降ると玄関の前に雨水が集中して落ちてきて、出入りの際にとても不便。雨樋の調子が悪いのかもしれないので見てもらいたい。」実際に現地調査を行ったところ、既存の雨樋が日焼けや経年劣化によって歪み・曲がりを生じており、正常に排水できていない状態でした。
その結果、本来であれば軒樋から縦樋を通じて排水されるべき雨水が、うまく流れずに玄関入り口に集中して落ちていました。
【工事の流れ】
①既存雨樋の取り外し
まず、歪んでしまった既存の雨樋を丁寧に取り外しました。
劣化が進んでいたため、接合部の状態も慎重に確認しながら作業を進めます。
②金具の追加設置
次に、新しい雨樋をしっかりと支えるため、金具を適切な間隔で追加設置しました。
これにより、雨樋のたわみや歪みを防ぎ、耐久性が大きく向上します。
③軒樋・縦樋の交換
劣化の目立っていた軒樋から縦樋にかけての部分を新しい雨樋に交換しました。
勾配を正しく調整し、雨水がスムーズに流れるよう施工しています。
④動作確認
工事完了後は、実際に水を流して排水状況を確認。
前に雨水が落ちることなく、スムーズに縦樋へと排水されることを確認しました。
→施工事例:雨樋一部交換工事、排水不良の改善|京都市北区の詳細ページ
施工事例 その2

【ご依頼内容】お客様より「天井が落ちそう」とのご相談を受け、現地にお伺いしました。
【対応】調査を行った結果、天井に雨染みがあり、天井裏がたわんでいる状態でした。しかし、現時点で雨漏りの形跡は見当たらなかったため、念のため散水調査を行いました。散水調査の結果、現在は雨漏りしておらず、数年前に行われた塗装工事により改善されていたことが確認できました。お客様より軒樋(のきどい)の交換もご希望いただいていたため、既存の落ち葉避けネットを一時的に取り外し、新しい軒樋へと交換いたしました。
→施工事例:雨漏り修繕|神戸市長田区の詳細ページ
雨樋の不具合で起きる具体的な被害
雨樋の不具合は見えにくい分、放置すると二次被害が深刻です。
代表的な症状と影響はこちらになります。
・詰まり(落ち葉やゴミ)→水があふれ外壁や窓枠が濡れる。シミ・カビの原因に
・ゆがみ・破損→正しく排水されず屋根や軒下に水がたまる
・外れ・落下→台風・強風で落下、雨漏りリスク増
・勾配不良→水の逆流で基礎や床下に水が入り込み構造材や断熱材を傷める
さらに、外壁や基礎が濡れるとシロアリ被害や腐食リスクも増加します。「屋根に異常はないのに雨漏りする」原因の多くは、実は雨樋にあるのです。一見小さな劣化や隙間でも、大雨や強風のときには一気に雨水が流れ込み、室内にシミやカビを発生させてしまうケースは少なくありません。
雨樋トラブルを早期発見するポイント
自宅で簡単にチェックできる症状はこちらになります。
✅雨樋から水があふれている
✅樋の継ぎ目から水が漏れている
✅雨樋に落ち葉や枝が詰まっている
✅雨の日に外壁や窓枠が濡れている
✅軒先に苔やカビが発生している
✅雨樋が外れてゆがんでいる
どれか一つでも該当したら、早めの点検・清掃・修繕が安心です。
台風・秋雨シーズンの今こそ点検を!
9月は台風や秋雨前線の影響で、雨樋トラブルが顕在化しやすい時期です。
放置すると雨漏りや外壁・基礎への二次被害が広がってしまいます。
アビリティでは経験豊富なスタッフが現場を丁寧に確認し、
詰まりや破損の有無、排水の状態必要な修繕や補修方法をわかりやすくご提案します。
大きな被害になる前に、まずはお気軽にご相談ください!

